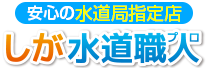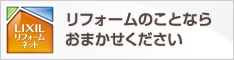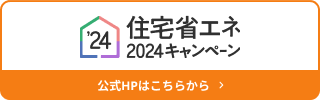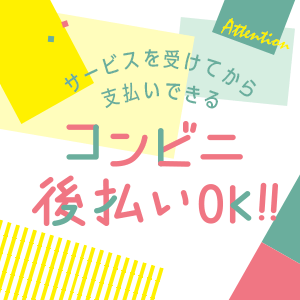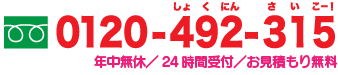水のコラム
洗面所・洗面台の水が流れない……?自分ですぐに試せる解消法をご紹介

朝の忙しい時間、洗面所の水がなかなか流れていかない……そんな経験はありませんか?
顔を洗った後の水が洗面ボウルにたまったまま、ゆっくりとしか排水されない様子を見ていると、朝からイライラしてしまいますよね。
実は洗面所のつまりの多くは、髪の毛や石鹸カスといった日常的な汚れが原因であることが多いんです。
ただこういった場合、特別な道具がなくても身近にあるものを使って意外と簡単に解消できる可能性も高いため、まずは冷静に状況確認することが大切。
今回は、割りばしとキッチンペーパーで作れる簡単な解消ツールや、市販のパイプクリーナーの効果的な使い方など、洗面所のつまりを自分で解消するための対処法について詳しくご紹介したいと思います。
洗面所の水の流れにストレスを感じている方。
まずはぜひ、この記事の方法を試してみてください。
洗面所のつまりを自分で直す方法
洗面所の水の流れが悪くなったとき、まず試していただきたいのが、身の回りにあるものを使った解消法です。
あわてて専門業者を呼ぶ前に、こういった手軽な方法で解決できることも多いため、ぜひ一度チャレンジしてみてください。
ちなみに、つまりの原因として最も多いのは「髪の毛」、次いで「石鹸カスや皮脂汚れ」や「小物類の落下」などが続きます。
それぞれ原因に応じた対処法があり、適切な方法を選ぶことでより効率的に解消できます。
まずは排水口のフタを外して、目に見える範囲でつまりの原因を確認してみましょう。
割りばしとキッチンペーパーで簡単除去ツール

排水口を覗いてみると、ヘアキャッチャーや排水口の奥に髪の毛がびっしり……なんてことはよくある光景です。
素手で取るのはちょっと気が引けるし、かといって放置すればどんどん悪化してしまいます。
そんなときに大活躍するのが、割りばしとキッチンペーパーで作る即席の除去ツール。
用意するもの:
- 割りばし
- キッチンペーパー:2~3枚
- 輪ゴム:2本ほど
作り方と手順:
- キッチンペーパーを割り箸の先端に巻きつける(2~3重に巻くのがおすすめ)
- 輪ゴムでキッチンペーパーをしっかり固定する
- 排水口のフタとヘアキャッチャーを取り外す
- 作ったツールを排水口に差し込み、ゆっくり回転させながら髪の毛を絡め取る
- 引き上げて付着した髪の毛を取り除き、2~3度繰り返す
- 最後に60℃程度のお湯をゆっくり流して仕上げ
キッチンペーパーの良いところは、適度な摩擦力があって髪の毛を絡め取りやすいこと。
濡れても破れにくいので、何度か繰り返し使えるのも便利です。
月に一度はこの方法で掃除をすると、大きなつまりを予防できますよ。
重曹×クエン酸で皮脂汚れを除去

目に見えない皮脂汚れや石鹸カスがつまりの原因となっている可能性も。
毎日の洗顔や歯磨きで流れる石鹸や歯磨き粉は、流し損ねると水に溶けきらず、少しずつ配管の内側に付着していきます。
これが積み重なることで、配管の通り道を狭くしてしまうんです。
そんな時に効果的なのが、重曹とクエン酸を使った除去法。
用意するもの:
- 重曹:50g(約1/2カップ)
- クエン酸(お酢などでもOK):大さじ2
- ぬるめのお湯(60℃程度):2リットル
- スプレーボトル(あれば)
- タオルまたはティッシュペーパー
掃除の手順:
- 排水口周りの水分をタオルやティッシュで拭き取る
- ぬるめのお湯にクエン酸を溶かしてクエン酸水を作る
- 重曹を排水口周辺と配管の内部にまんべんなく振りかける
- その上からクエン酸水を振りかける(すぐにシュワシュワと発泡が始まる)
- 発泡した状態で15~30分ほど放置する
- お湯でゆっくりと泡と汚れを流す
- 水がスムーズに流れることを確認する
重曹とクエン酸が反応して生まれる炭酸ガスが、配管内の汚れを浮かせて流しやすくしてくれます。
月に2回程度行えば、配管を清潔に保つことができますよ。
ラバーカップ(すっぽん)の正しい使い方

ラバーカップは洗面所のつまりにも効果的な道具ですが、正しく使わないと効果が半減してしまいます。
特に重要なのは、洗面台のオーバーフロー穴(洗面ボウル上部の小さな穴)を濡れタオルなどでしっかり塞ぐこと。
これをしないと圧力が逃げてしまい、つまりが解消できません。

使い方は簡単で、洗面ボウルに5cmほど水を溜め、ラバーカップを排水口に密着させます。
その後ゆっくりと押し込んで空気を抜き、勢いよく引き上げる動作を5~10回程度繰り返すだけ。
成功すると、ゴボゴボという音とともに水が流れ始めるはずです。
ポイントは「引く時に少し勢いをつける」こと。
つまりの原因を吸い上げるイメージで操作すると効果的です。
最後にお湯を流して仕上げれば完了。
100円ショップでも購入できるので、トイレとは別で洗面台用にも一つ持っておくと安心ですね。
ラバーカップの代わりにペットボトルでも
ラバーカップが自宅に無かったり、「トイレ用のラバーカップを洗面台に使うのはちょっと……」という方も多いはず。
実は、ペットボトルを使って同じような効果を得る方法があるので、その代替案についてもご紹介しておきましょう。
用意するもの:
- 2リットルのペットボトル(柔らかめのものがベスト)
- タオル
具体的な手順:
- オーバーフロー穴を濡れタオルでしっかり塞ぐ
- ペットボトルの口を排水口に突っ込む
- 排水口の隙間を埋めるように周囲を濡れタオルで塞ぐ
- 洗面ボウルに5cmほど水を溜める
- ペットボトルを押しつぶしたり戻したりを何度か繰り返す
- その後ペットボトルを一気に引き抜き、何度か繰り返す
- 最後にお湯を流し込んで仕上げ
ペットボトルの柔軟性を利用して、ラバーカップと同じように圧力差を作り出す仕組みです。
ただし、ラバーカップほどの吸引力はないので、軽度のつまり以外には効果が薄い点には注意が必要です。
排水トラップの分解清掃

ここまでの方法を試しても改善しない場合、排水トラップ内部に汚れが蓄積している可能性があります。
排水トラップとは、洗面台下にあるS字型やP字型に曲がった配管のことで、水を溜めておくことで下水の臭いを防ぐ役割があります。
ただ、その構造上、曲がった部分に汚れが溜まってしまうこともよくあるんです。
まず、洗面台下の扉を開けて排水管を確認してみましょう。
S字型は床に向かって下りていく形、P字型は壁に向かって横に伸びる形をしています。
どちらのタイプでも、重要なのは「清掃口」があるかどうかです。

トラップの一番下の部分(S字)または側面(P字)に、丸いキャップのようなものがあればそれが清掃口です。
手で回せそうなキャップがあれば自分でも簡単に清掃可能ですので、ご紹介する手順にそって一度チャレンジしてみてください。
清掃口がある場合の清掃手順
用意するもの:
- バケツ(水や汚れがこぼれるため必須)
- ゴム手袋
- 古いタオル
- 歯ブラシなど
手順:
- まずは事前準備
清掃口の真下にバケツなどの容器を設置しましょう。
念のため、床にタオルを敷いておくとさらに安心です。 - 止水栓を閉める
洗面台の下の止水栓を時計回りに閉める。 - 清掃口を開ける
キャップを反時計回りにゆっくり回します。
開けた瞬間、水や汚れが出てくるので注意しましょう。 - 内部を清掃する
配管の内部に溜まった汚れを掻き出します。
歯ブラシなどを使うと効率よく清掃できます。 - キャップを戻す
最後にしっかりキャップを締めて水漏れが無いかチェック。
清掃口がない場合
清掃口がないタイプは、少し特殊な工具や知識が必要で、配管全体を分解する必要があるためパッキンの劣化や配管の破損リスクが高くなります。
無理に分解しようとすると、かえって大きなトラブルになることも……。
このタイプの場合は、基本的には専門業者に相談することをおすすめします。
洗面所でやってはいけないNG行動!

つまりを解消しようと焦って、かえって洗面台や配管を傷めてしまうケースがよくあります。
やってはいけないNG行動を知っておくことで、さらなるトラブルの連鎖を防ぎましょう。
熱湯は絶対NG!適温は60度まで
「熱いお湯の方が汚れが落ちそう」と思って、沸騰したお湯を流そうとしていませんか?
実はこれ、洗面台にとって絶対にやってはいけないNG行動のひとつなんです。
陶器製の洗面ボウルの場合、急激な温度変化でひび割れを起こすことがあるため、最悪の場合洗面台ごと交換が必要になる可能性も。
また樹脂製の排水管やパッキンなども熱湯により変形する恐れがありますので、熱湯の使用は絶対にやめましょう。
お湯を流す場合の適温は60℃程度。
給湯器の設定温度で調整するか、沸騰したお湯に同量の水を混ぜれば、ちょうどいい温度になります。
針金ハンガーの使用は慎重に
つまり解消のテクニックとして紹介されることもある針金ハンガーですが、実は配管を傷つけてしまうリスクが高いことも覚えておきましょう。
特に樹脂製の配管は傷つきやすく、そこから水漏れの原因になることも。
使う場合は、先端に布を巻くなど、配管を保護する工夫が必要です。
パイプクリーナーの効果的な使用法

市販のパイプクリーナーは手軽に購入できて便利な反面、どれを選べばいいのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
一口にパイプクリーナーと言ってもいくつか種類があり、洗面所のつまりに適したものを選ぶことで、効果も全く変わってきます。
ドラッグストアやホームセンターの棚を見ると、各メーカーから色々な種類のパイプクリーナーが提供されており、値段も300円から1,500円程度まで幅広く取りそろえられていますよね。
安いものだと効果がないのか……かといって高いと毎回使用するにはコスパが……なんて悩んでしまいがち。
そういった疑問を解決しつつ、パイプクリーナーを最大限活用する方法をご紹介します。
市販のパイプクリーナーの選び方
パイプクリーナーを選ぶときのポイントは、まず「何を溶かしたいか」を明確にすることです。
洗面所のつまりの主な原因は髪の毛と石鹸カスなので、これらに効果的な成分が入っているかをチェックしましょう。
| タイプ | 液体タイプ | ジェルタイプ | 粉末タイプ |
|---|---|---|---|
| 特徴 | ・サラサラで即効性あり ・配管の奥まで届きやすい |
・粘度が高く壁面に張り付く ・じっくり汚れを分解 |
・水と反応して発熱 ・強力な洗浄力 |
| 適した汚れ | ・軽度のつまり ・日常の予防掃除 |
・髪の毛、ヘドロ状の汚れ ・洗面所に最適 |
・頑固な油汚れ ・長期間の蓄積汚れ |
| 価格帯 | 300~500円 | 500~1,000円 | 1,000~2,000円 |
| 注意点 | ・効果は穏やか ・頑固なつまりには不向き |
・目や皮膚への付着に特に注意 ・臭いが強め |
・発熱するため取り扱い注意 ・素材を選ぶ |
洗面所のつまり対策としておすすめなのは、髪の毛への効果が高く、扱いやすいジェルタイプです。
100円ショップのものでも一定の効果はありますが、つまりがひどい場合は、ドラッグストアなどで売っている効果の高いものを選ぶと違いを実感できるはずです。
人気製品の特徴と選び方
実際に店頭でもよく見かける定番品の中から使いやすいものをいくつかご紹介しておきましょう。

ジェルタイプの定番としては「パイプハイター 高粘度ジェル(花王)」などが有名です。
ドラッグストアには必ずといっていいほど置いてある定番商品で、粘度が高く、垂直な配管にもしっかり張り付いて髪の毛を溶かしてくれるのが特徴。
迷ったらこれを選んでおけば間違いない、と言える商品のひとつです。

また頑固なつまりには「ピーピースルーF(和協産業 )」が効果的です。
粉末タイプで、業務用にも使われるほどの強力な洗浄力があります。
ただし、発熱するため取り扱いには十分な注意が必要です。

予防的な使用や軽いつまりには「パイプユニッシュ(ジョンソン)」も人気です。
800gの大容量版もあってコスパが良く、定期的なメンテナンスに向いています。
香りも比較的マイルドなので、使いやすいと評判の商品ですね。
これらの製品は、ドラッグストアやホームセンターで手軽に購入できます。
どれを買えばいいのか迷った際は、ぜひ参考にしてみてください。
パイプクリーナーの効果的な使い方
パイプクリーナーの効果を最大限引き出すには、正しい手順を踏むことが重要です。
見落としがちなポイントを押さえるだけで、効果は格段に上がります。
使用手順:
-
事前準備
排水口周りの水分をティッシュやタオルで完全に拭き取りましょう。
水が残っていると薬剤が薄まって効果半減です。 -
薬剤をそそぐ
排水口の壁面に沿わせてゆっくりと流し込みます。
勢いよく入れると薬剤が流れてしまい効果が薄れてしまうため注意。 -
放置時間を守る
製品記載の時間を厳守しましょう(通常30分~1時間程度)。
タイマーをセットして正確に測っておくことをおすすめします。 -
仕上げにお湯で流す
最後に60度程度のお湯を2~3回に分けて流します。
一気に流すより、ゆっくりと流し込むのが効果的です。
「長く置けば効果的」は間違い!
長時間放置すると溶けた汚れが再び固まることがあります。
使用時の注意点
パイプクリーナーは強力な薬剤なので、安全に使うための注意点をしっかり守りましょう。
まず絶対に守らなければならないのが「まぜるな危険」の表示。
効果がなかったからといって、続けて違う製品を使うのは本当に危険です。
万が一、酸性とアルカリ性の製品が混ざると、有毒ガスが発生する可能性がありますので絶対にやめてください。
換気ももちろん忘れずに。
洗面所は狭くて密閉された空間なので、薬剤の臭いがこもりやすくなります。
窓があれば開けて、なければドアを開けて換気扇などで空気を循環させるなどの工夫が必要です。
また、アルミ製の部品や大理石の洗面台には使用できない製品もあります。
最近の洗面台には様々な素材が使われているので、不安な場合は目立たない部分で試してから使用するといいでしょう。
注意点まとめ
- 必ず換気をする(窓を開ける or 換気扇を回す)
- ゴム手袋を必ず着用する
- 他の洗剤と絶対に混ぜない(違う製品を試す場合は最低1日は間を空ける)
- 目や皮膚に付着したら大量の水ですぐに洗い流す
- 洗面台の素材との相性を確認する
排水管の洗浄剤については、Youtube動画でも詳しくご紹介していますので、具体的な使い方や効果の違いについて知りたい方はぜひ参考にしてみてください!
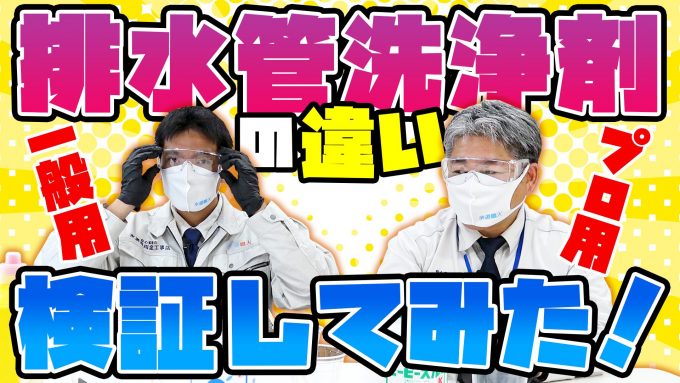
【こんなに違う!】市販品と業務用、排水管洗浄剤の効果の違いを徹底検証!:水道職人チャンネル
洗面所・洗面台つまりを予防する日常メンテ術

無事に洗面所のつまりを解消できたなら、もう二度と同じ苦労はしたくないものです。
そのためにも、日頃のちょっとした心がけで、洗面所のつまりを予防しておきましょう。
大掃除のときに一気に頑張るよりも、毎日の小さな習慣の方がずっと効果的です。
そこで今回は、無理なく続けられる予防法についてご紹介したいと思います。
毎日1分でできる予防習慣
-
使用後に熱めのお湯で流す(10秒程度)
洗面台を使い終わったら、60℃くらいのお湯を10秒ほど流すだけ。
これだけで、石鹸カスや皮脂が固まる前に流れてくれます。
朝の洗顔後と夜の歯磨き後、この2回だけでも非常に効果的です。 -
髪の毛はその場で処理する
朝のヘアセットなどの後、抜け毛が洗面ボウルに落ちていたら、その場でティッシュでさっと拭き取りましょう。
ヘアキャッチャーに溜まった髪の毛も、気づいたときにすぐ取り除くように。
「後でまとめて」と思っていると、石鹸カスと絡まって取りにくくなってしまいます。 -
排水口周りを拭き取る
歯磨き粉や洗顔料が排水口の周りに残っていると、それが核となって汚れが蓄積していきます。
使用後にさっと水で流し、できれば軽く拭き取っておく習慣をつけておきましょう。
週/月に1度の定期メンテナンス
毎日の習慣に加えて、週1回、月1回の定期メンテナンスも意識しておくことで、汚れが原因の洗面所つまりとはほぼ無縁に。
週1回のメンテナンス:
- ヘアキャッチャーを外して歯ブラシで掃除(裏側も忘れずに)
- 排水口の見える部分を歯ブラシでこする
- 重曹とクエン酸を大さじ2~3ほど振りかけて10分後にお湯で流す
月1回のメンテナンス:
- 市販のパイプクリーナーで予防洗浄(つまる前に使うのがポイント)
- オーバーフロー穴を綿棒で掃除(カビが溜まりやすい)
- 排水口パッキンの状態確認(ひび割れがあれば早めに交換)
定期的なメンテナンスを行うことで、大きなトラブルを未然に防ぐことができます。
予防的な清掃は、つまってからの対処より遥かに簡単です。
関連記事すぐに汚れる洗面所、きれいに保つにはどうすればいい?
つまりやすい洗面台の特徴は?
最近の洗面台はデザイン性が高くて素敵なものが多いんですが、実はタイプによってつまりやすさもある程度異なります。
自宅の洗面台がどのタイプか知っておけば、より効果的な掃除やメンテナンス習慣を意識できますよ。
洗面台のタイプ一覧
洗面台と言っても色々なタイプに分かれています。
自宅の洗面台タイプに合わせて、適したメンテナンスやお掃除を心掛ければ、つまりのトラブルも大幅に減らすことができます。
| タイプ | 特徴とメリット | デメリット |
|---|---|---|
| オーバーカウンター(はめ込み)型 | ・最も一般的で価格が手頃 ・自分での交換が可能 ・多くのカウンターに対応 |
・リム(縁)部分に汚れが溜まりやすい ・リム周りの掃除が必要 |
| スリム型 | ・省スペース設計で洗面所が狭くても使いやすい ・奥行き40-50cmでコンパクト ・圧迫感が少ない |
・ボウルが小さく水はねしやすい ・排水管が細くつまりやすい ・収納スペースが限られる |
| ボウル一体型 | ・継ぎ目がなく掃除が簡単 ・見た目がスッキリ美しい ・汚れが溜まる隙間がない |
・価格が高い(12万円~) ・部分的な修理が困難 ・素材の選択肢が限られる |
| 置き(ベッセル)型 | ・デザイン性が高くおしゃれなものも多い ・素材やデザインが豊富 ・個性的な空間演出が可能 |
・接合部に汚れが溜まりやすい ・ボウル底面の掃除が困難 ・水はねが多い |
オーバーカウンター(はめ込み)型洗面台

最も一般的なタイプで、カウンターに開けた穴にボウルをはめ込む方式です。
自分での交換も可能で、価格も手頃なのが魅力。
ただし、ボウルの縁(リム)がカウンターの上に出ているため、この部分に髪の毛や汚れが溜まりやすいのが難点と言えます。
リム周りの掃除を怠ることで、そこから汚れが広がり、排水口や配管のトラブルにつながることも。
スリム型洗面台

省スペース設計で人気のスリム型は、奥行きが40~50cmと通常より約10cm浅くなっています。
マンション・アパートなどの集合住宅では定番の選択肢ですが、その分ボウルも小さく、排水管も細めになっているのが特徴です。
狭いボウルに髪の毛や石鹸カスが集中しやすく、配管回りもコンパクトに納められていることも多いため、ちょっとしたつまりでも大きなトラブルに繋がるケースも。
こまめな清掃やメンテナンスが大切です。
ボウル一体型洗面台

カウンターとボウルが一体成型された、継ぎ目のないタイプです。
人工大理石やセラミックで作られることが多く、見た目の美しさと掃除のしやすさが最大の魅力。
汚れや髪の毛が引っかかる場所がないので、サッと拭くだけで清潔を保てます。
ただしリムが無い分、カウンターの汚れもまとめて直接排水口に流してしまう方も多く、それがつまりの原因になる可能性も多いんです。
このくらいなら……と排水口に流してしまわずに、きちんと処理するよう心掛けましょう。
置き(ベッセル)型洗面ボウル

カウンターの上にボウルを置くタイプで、ホテルライクな雰囲気が人気です。
陶器やガラス、天然石など素材も豊富で、インテリアのアクセントになります。
ただし、ボウルとカウンターの接合部が細くなっていたり、特殊な繋ぎ方になっているタイプもあるため注意が必要。
おしゃれな反面、お手入れには少し手間がかかります。
自己解決できないつまりの見極め方

ここまでご紹介した方法を一通り試してみたけれど、まだ水の流れが改善しない……そんなときは、より深刻なトラブルが隠れている可能性があります。
無理に自分で解決しようとすると、かえって状況を悪化させてしまうことも。
私たち「しが水道職人」でも、「最初は軽いつまりだったのに、いろいろ試しているうちに完全に流れなくなってしまった」といったご相談をいただく機会は少なくありません。
また配管の奥や排水の仕組み自体に異常がある場合など、自分ではなかなか対処ができないケースも多いため、ご不安がある場合はぜひ一度私たちにご相談ください。
洗面所に関するトラブルの実例①
大津市のお客さまより、洗面台の水が全く流れなくなったとのご相談を受けご自宅へ伺いました。
ご自身でパイプクリーナーなども試されたそうですが改善が見られず、現地調査の結果、排水管の奥で汚れが完全に固まっている状態でした。
薬剤処理後、高圧ポンプでつまりを除去し、約30分ほどで解決。
このように完全につまってしまった状態では、市販の洗浄剤やグッズなどではなかなか対処が難しいものです。
関連記事洗面排水のつまり除去:作業実施レポート(滋賀県大津市)
洗面所に関するトラブルの実例①
米原市のお客さまからも、水が流れなくなってしまったため解消してほしいとのご依頼がありました。
薬剤では改善しなかったため、高圧洗浄機で配管を洗浄後、トラップも分解して確認。
奥から出てきたのはなんと果物の種でした。
こうした小さな異物でも、それを核として汚れや皮脂などが固まり、やがてつまりの原因に繋がってしまいます。
関連記事洗面所の排水管洗浄:作業実施レポート(滋賀県米原市)
こんな症状には要注意!プロに依頼すべきサイン
洗面所に関するトラブルの中でも、自分での対処が難しく、プロに依頼した方がよい症状についてまとめてみました。
こういったサインが出た場合は、無理をせず専門業者への相談を検討してください。
プロへの依頼を検討すべき5つのサイン
- 複数の排水口が同時に調子が悪い
洗面所だけでなく、お風呂やキッチンの排水にも違和感がある
→排水管の本管に問題がある可能性大 - ゴボゴボという異音が続く
水を流すたびに変な音がする
→配管内の空気の流れに問題があるケースも - 悪臭が消えない
排水口から下水臭が上がってくる
→排水トラップの破損や劣化の可能性 - 水が完全に流れない・逆流する
最も緊急性が高い症状
→無理な対処は汚水溢れの危険も - 月2回以上、同じ症状を繰り返す
一時的に改善してもすぐに再発する
→配管の設計や劣化など根本的な問題の可能性
緊急時の応急処置と二次被害の防止法
プロに依頼することを決めたら、到着までの間に被害を最小限に抑える応急処置をしておきましょう。
慌てて間違った対処をすると、かえって状況を悪化させてしまうこともあります。
まず最初にやるべきは「止水栓を閉める」ことです。
洗面台の下の扉を開けると、壁から出ている2本のパイプがあるはず。
それぞれに付いているハンドルを時計回りに回すことで水を止めることができます。
これで万が一の水漏れを防げるので、必ず覚えておいてください。
次に、排水管の下にバケツやたらいなど水を受けられる容器を置いておきましょう。
大きめの鍋でも構いません。
もし配管から水が漏れ始めても、これで床への被害を防ぐことができます。
バケツの下にはタオルや新聞紙を敷いておくと、さらに安心ですね。
最後に、症状の記録を取っておくと、依頼時の説明がスムーズになります。
スマートフォンなどで動画を撮っておくのが一番分かりやすいですね。
排水口のアップだけでなく、洗面台全体の写真も撮っておくと、型番確認や部品準備に役立つためおすすめです。
止水栓が固くて回らない場合は、無理に回そうとせず、元栓(水道メーター付近)を閉める方法もあります。ただし、家全体の水が止まるので注意が必要。
関連記事洗面所の水のトラブルに落ち着いて対応するために知っておいてほしいこと
安心できる水道業者の選び方

「どの業者に頼むべきか」というのも悩みがちなポイントでしょう。
残念なことですが、世の中には高額な請求や不必要な工事を勧めてくる悪質な業者が存在するのも確かです。
「広告には○○円と書いてあったのに、実際には説明も不十分のまま10万円以上請求された……」なんて話も……。
ただ、ご安心ください。
しっかりとポイントを押さえておくことで、信頼できる業者を選ぶことは可能です。
大切なのは、トラブルに見舞われても焦って選ばず、冷静に判断すること。
今回は、安心して任せられる業者の見分け方について具体的にご紹介しておきたいと思います。
業者選びで押さえておきたい5つのポイント
良い業者を選ぶには、いくつか重要なチェックポイントがあります。
中でも特におさえておきたいのがこの5つです。
- 水道局指定工事店であること
- 事前の見積もりが明確
- 丁寧な説明
- 施工実績の確認
- アフターフォロー体制
これらを一つ一つ確認していけば、トラブルに巻き込まれる可能性はぐっと低くなるはずです。
1. 水道局指定工事店であること
まず確認したいのが「水道局指定工事店」の認定を受けているかどうか。
これは各自治体の水道局が、技術力と信頼性を認めた業者にだけ与えられる資格です。
指定番号は必ずホームページや名刺などに記載されているはずなので、一度確認してみてください。
一概に指定を受けていない業者が悪いわけではありませんが、一つの安心材料になることは確かです。
参考ページ大津市:大津市指定給水装置工事事業者一覧表及び水道工事について
草津市:指定給水装置工事事業者一覧
2. 事前の見積もりが明確
優良業者は、作業前に必ず見積もりを提示してくれます。
「解体してみないとわからない」「とりあえず作業してみましょう」という業者は要注意です。
また、見積もりが有料か無料かも電話の時点で確認しておくと安心です。
3. 丁寧な説明
症状の原因は何なのか、どんな作業が必要なのか、なぜその金額になるのか。
これらを専門用語を使わずに、できるだけ分かりやすく説明してくれる業者を選びましょう。
質問に対して曖昧な返答しかなかったり、専門用語ばかりでまくし立てるような業者は避けた方が無難でしょう。
4. 施工実績の確認
ホームページなどで過去の施工事例を公開している業者は、自分たちの仕事に誇りを持っている証拠。
特にビフォーアフターの写真や、具体的な作業内容が記載されていると安心して依頼しやすいですよね。
他にも口コミサイトやGoogleレビューも参考になりますが、極端に良い評価や悪い評価だけでなく、中間的な評価の意見も読んでみることが大切です。
5. アフターフォロー体制
作業後の保証期間はどのくらいか、万が一再発した場合はどう対応してくれるのか。
こういったアフターフォローについて、きちんと説明がある業者を選びましょう。
「うちは絶対に再発しません」などと言い切る業者より、「万が一の場合はこう対応します」と具体的に説明してくれる業者の方が信頼できますよね。
見積もり時に確認しておきたい項目
見積もりを取る際は、金額だけでなく内容もしっかり確認することが重要です。
後から「こんなはずじゃなかった」とならないよう、以下の点を重点的に、必ず確認しておきましょう。
作業内容が明記されている
「つまり除去作業一式」といった曖昧な表記では実際に何をするのかが分かりません。
できれば、「高圧洗浄機による排水管清掃 ○○メートル分」「薬剤洗浄 ○回」など、具体的な作業内容が記載されている見積もりを依頼するようにしましょう。
もちろん、事前の説明と食い違っていないかの確認も忘れずに。
追加料金の有無
追加料金が発生するかどうかも重要なポイントです。
基本料金、出張費、深夜料金、部品代、廃材処理費など、追加で発生する可能性のある費用についても事前に確認しておきましょう。
「作業してみないとわからない」という部分があるのは仕方ありませんが、その場合でも「最大でいくら程度になる可能性があるか」といった見込み料金は聞いておくと安心です。
保証範囲の確認
施工後の保証範囲の確認も忘れずに。
作業後どのくらいの期間保証があるのか、保証の適用条件は何か、保証書などは発行してもらえるのかなど、口頭ではなく必ず書面で確認することが大切です。
トラブルを避けるための事前準備
業者とのトラブルを避けるにも、依頼する際の事前準備もしておくと安心でしょう。
ちょっとした工夫で、スムーズな取引ができるようになります。
まず、写真や動画撮影などで症状を記録しておくことは本当に重要です。
つまりの状態、水の流れ具合、異音がする場合はその様子を動画で撮影しておきましょう。
これがあれば、電話での問い合わせ時にも正確な情報を伝えられますし、複数の業者に相談する際も同じ説明ができるため手間を省くことができます。
料金が高額になるケースなどは、複数の業者で見積もり(相見積もり)してもらうことも検討すると良いかもしれません。
緊急性が高くない場合は、2~3社から見積もりを取ることで相場感も分かります。
その際、「今すぐ決めれば割引します」といった営業トークには要注意です。
安心できる業者であれば、よっぽどの緊急事態でもない限りはじっくり検討する時間を取ってくれるはずです。
洗面所のことで困ったら「しが水道職人」へ!

ここまでご紹介した方法を試しても解決しない場合や、「自分でやるのはちょっと不安……」という方は、ぜひ私たち「しが水道職人」にお任せください。
滋賀県内全域にて、皆様の水回りのトラブルを解決しています。
24時間365日体制で受け付けており、急なトラブルにも迅速に対応いたします。
水道局指定工事店として、皆さまに安心してご相談いただけるよう、作業前には必ず丁寧な説明と無料のお見積もりを提示し、しっかりとご納得いただいてからの作業を徹底しております。
もちろん、アフターフォローも充実しており、作業後の不安も解消いたします。
地域に根差したサービスのご提供を心掛けており、滋賀の皆さまに頼っていただけるよう、日々技術の向上に努めております。
お困りの際はぜひ、お気軽にお問い合わせください!